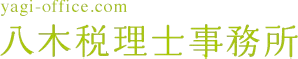お知らせnews
八木税理士事務所について about us

かかりつけ税理士として業務サポートを行います
税金と経理の仕事を始めて30年になり、おかげさまで事務所も開業20周年をむかえました。
その間、多くの経営者様と一緒に仕事をさせていただきましたが、経営上の問題や、税理士に対するご要望は、経営者様によって様々でした。
経営者様一人一人としっかり向き合い、必要とされるサービスをご提供すると共に、専門家としての立場から前向きなご提案を行い、
ご事業の発展をお手伝いしたいと考えております。
業務内容service

セカンドオピニオン
税理士にも得意分野と不得意分野がありますし、税理士の仕事をサービス業だと思っていない税理士も大勢います。もしご自分の会社やご商売が心配になりましたら、是非一度弊所にご相談下さい。初回無料で対応させていただきます。
お客様の声 voice
ご利用いただいているお客様の声をご紹介します。
-

東京都のA社長様
より多くの資金を集め、様々な事業への進出をご希望。【社長様の声】
創業時からお世話になって、来年はついに10期目を迎えようとしています。経営の素人がゼロから始める危なっかしいチャレンジだったにも関わらず、これまでずいぶんと辛抱強く面倒をみていただきました。どんなときも自信を持って前進していける姿勢を維持することは、企業経営にとって重要な条件だと思います。大切な経営判断の局面においても、常に傍らにいてくださることに感謝しています。 -
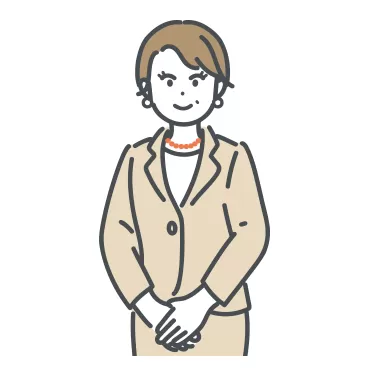
東京都のK社長様
脱サラされて会社設立。【社長様の声】
開業当初の苦しい時期に、「会社もお子さんもこれからだから。」と、お支払いできる料金で親身にサポーしていただきました。
八木先生も子育ての真っ最中だそうで、同じ生活感のもとで一緒にやっていけて安心できます。 -

埼玉県のK社長様
脱サラされて独立開業。【社長様の声】
経営のこと、税金のこと、分からないことはなんでも八木先生に相談しています。税金に関する専門的な事柄についても、例を交えて分かりやすく教えていただけますし、適切なアドバイスをいただけますので、100%信頼しています。八木先生のおかげで、不安を抱えることなく仕事に集中することができています。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問Q&A
お客様よりよくいただく質問をまとめました。
「料金の相場っていくら位ですか?」「とりあえず、ご相談したいのですが?」「起業しましたが、経理の仕方がわかりません。」など、気になる方は下記ボタンよりチェックしてみてください。
代表あいさつ greeting

八木 隆昌(やぎ たかよし)
都下の事務所という性質上、中小企業様~個人事業主様の「かかりつけ医」のような形で 業務を行ってきました。メーカーの営業職を務めた経験を活かし、「作る側・売る側」の視点に立ったサポートを心がけています。ご事業の発展だけを考えるのではなく、経営者様やご家族や一緒に働く方々が、どうしたら幸せになれるのか、常に考慮しながら仕事をしています。